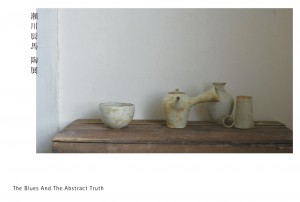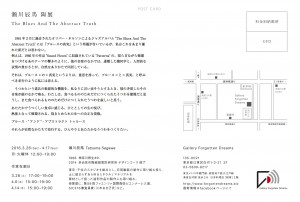573℃
岐阜で陶芸の勉強をしていた学生時代、その授業の殆どが実習だったが、週に1度、釉薬や陶土の科学的な性質を学ぶ、純粋な座学があった。
日差しの入らないリノリウム床の教室で授業は行われ、学校に併設された窯業科学センターに務める研究者が教鞭を執った。
背が高く、古い形のメタルフレーム眼鏡を掛けた中年の男で、その繊細そうに響く小さな声が、いかにも研究者らしかった。
恐らく彼の職能上の興味はその教室から(あるいはその小さな地方都市からも)遥か遠いところにあったのだろうが、彼は職業上の義務として授業を遂行したし、我々もそれを義務として聴講した。
ある日のその授業で配られたハンドアウトに、こういう記述があった。
“粘土中に含まれる石英の結晶構造は573℃を境に変化を起こし、低温型のα-石英から高温型のβ-石英に転移する”
水に浸せば柔らかくなる粘土が、その温度を境に、陶というマテリアルへと不可逆的に変化を遂げてしまう。
その事実はとても新鮮で、奇妙なほど具体的に定義された573℃という数字と相まって、深く印象に残っている。
– – –
今暮らしている自宅兼アトリエは、元々はYさんという陶芸家がその晩年に自分のために設えたものだ。
数年前にYさんが亡くなり、売りに出ることになったところに縁あって出会い、集落全体が低山にぐるりと囲まれた、貝のなかのように静かなその環境に惹かれて、見に行った日に移住を決めた。
生前のYさんとの面識は一切なく、移住してから、その人となりを周囲の人々から少しずつ知ることになった。
移住を決めて間もないころだったと思う。
ある展示で在廊した際に、ギャラリストのIさんとの会話のなかで移住先の話題になり、Iさんが若かりし頃のYさんに雑誌の取材で会いに行ったことがあるということが分かり、お互いに声をあげて驚いた。
後日、Iさんはその時の取材記事を手渡してくれてた。
1975年に発行されたその工芸雑誌の紙面には、27歳のYさんの姿があった。
木こりみたいにがっしりとした体格を、どこか言い訳するような感じで小さく丸め、秋草の中で内面的にはにかむ青年。
偶然にも、当時の僕も、27歳になったところだった。
インタビューの中でYさんは、
自分の生まれ育ったこの地に、窯を造る準備をしているところなんです
と語っていた。
– – –
Yさんから受け継いだアトリエには、三十数年前にYさんが自らの手で築窯した穴窯がある。
仕事の合間に時間を見つけては、この1年、窯の手入れを進めていた。
砂に塗れた窯を掃き清め、その全体像を手探りで確かめていく時間は、陶芸家のそれというよりは殆ど考古学者のようで、どこにも見当たらなかったダンパーを地中から掘り当てた時には、喜びと安堵でひとり声をあげて笑ってしまった。
Yさんの遺した穴窯を手探りで理解していく作業は、ある意味ではYさんという人間を理解する作業でもあったように思う。
ロストルの大きさや、ダンパーや色見の位置の設計を通して、彼が作家としてどういう種類の美しさを手に入れようとし、またなにを必要のないものとして手放していったのか、感じ取れるような気がした。
窯場で作業をしていると、様々なひとに声を掛けられた。
左党だったYさんがつくる酒器が、いかに優れたものであったかを語るひと。
アトリエで行われた作品展を目当てに、東京からのバスツアーが組まれたときの様子を得意げに語るひと。
高校の後輩で、Yさんの後を追いかけるように自身も陶芸家となったひと。
彼の周縁に遺された、ディティールに富んだ様々なピースは今も生暖かく脈打ち、ただYさんという中心だけが、真空のような沈黙のなかに在った。
– – –
年末、手直しした穴窯で、初窯を焚いた。
これまで電気窯での制作経験しかない僕にとって、それは未知の地へと踏み出していくタフな旅であると同時に、土を焼くということの原点への帰郷であったようにも思う。
冷めるのも待ちきれず、炉内から鉄棒で小さな花器を引っ張り出し、光のなかに抱きとめたそのときに。
ある不可逆的な変化が自分に訪れたことを直感的に理解した。
近似値で言葉にするならそれは、自分が使い古していた辞書の大事な頁の内容が、ある朝突然に書き換わってしまったようなものかもしれない。
これまで自分にとって重要な意味を持っていたはずのテクストたちはその明瞭な意味を失い、代わりにこれまでうまく読むことの出来なかったテクストたちが、唐突に輝きを帯び始める。
573℃を超えた石英が、アルファからベータへと転移するように。
唐突に授けられた、暴力的なまでに不可逆なこの変化の跡に、今はただ立ち尽くしている。
– – –
初窯をはじめる日の朝、火の神様への祝詞の代わりに、長田弘のファイアカンタータという詩を窯前で朗読した。
火の祝福と畏敬を詠ったその美しい詩は、このようにして結ばれる。
三本の蝋燭が、われわれには必要だ。
一本は、じぶんに話しかけるために。
一本は、他の人に話しかけるために。
そしてのこる一本は、死者のために。